|
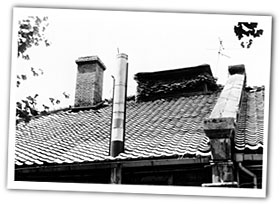 たとえば「用」。
たとえば「用」。
わたしたちの身の回りのものはすべて何らかの用を担っています。それは空間についてもいえて、実用から無用の用まであらゆる用が空間を規定しているといえるでしょう。 すなわち用は、それを知ることでその空間の成り立ちが推測できるものなのです。
また、かつて柳宗悦らが民具の用の中に美を見出したように、わたしたちは空間においても用の中に美しさという別の価値を見いだすことができます。内から外、外から内への視線を制御する京都の町屋の格子を挟んだ内外空間や、奥に長い町屋の中での動線を担う土間などはその具体例としてよく挙げられるものです。
そしてわたしたちは用の中に価値を見出すと同時に、その外にも注目することができます。ニューヨークや香港などのきらめく夜景は経済という用がもたらしたものですし、農家の白く陽を跳ね返す、踏み固められた土の前庭は竜安寺の石庭とは違って農作業のためにあったのですが、それらにわたしたちが見出すのは機能美ではなく用の外側にある価値でしょう。
さらに、機能が生み出したかたちが時の蓄積の中で醸成され、機能を果たしながらもそこに生きられたひとへの感慨を引き出すことのできる産業遺産や製鉄所の巨大な溶鉱炉、山の斜面にへばりつく棚田といったものへのまなざしは用の内外両方を睨んだものと考えられるでしょう。
このように考えてみると用のために働く部分と、そうでない部分との両方が備わること(→かくす、きえる)が今日、わたしたちがそこに空間を見出す前提となっているように思います。かつて機能的ということが空間であるための必要条件だったときがあり、やがてそれが十分条件となって、そして必要十分条件になったということでしょうか。
京都市左京区吉田(写真:加藤聖子) |