|

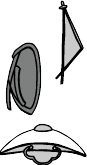 古来よりわれわれの建築には金物の釘は使われないか、または見えないところに使う工夫があった。どうしても露出するところには「釘隠し」という手法でむしろ積極的な造形上のアクセントとしている。これらはすべてディメリットをプラスに生かす発想の転換にほかならない。
古来よりわれわれの建築には金物の釘は使われないか、または見えないところに使う工夫があった。どうしても露出するところには「釘隠し」という手法でむしろ積極的な造形上のアクセントとしている。これらはすべてディメリットをプラスに生かす発想の転換にほかならない。
引き手も同様に、造形を考慮したものの中には、その機能としての記号性が消失するかのような例も見られる。
写真左:桂離宮 引き手
写真右:曼殊院 富士の間 釘隠し

|
部分が全体を支配するとき
|

二条城大手門のリベット
その発祥がもともと軍事施設である「城」としてのアイデンティティを示すものとして、防火上、保護上の機能面のみならず、その規則性のある配列が造形上のポイントとなっている点も見逃せない「部分への視点」。
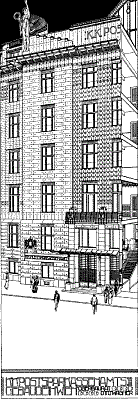 オットー・ワーグナーの見た未来
オットー・ワーグナーの見た未来
ところはウィーン、時はまさにゼセッションの波が押し寄せるころ、ワーグナーの胸にはまぎれもなく「いまだ見ぬ未来」が宿っていた。
モチーフはリベットというより、規則性を表現するドットのようであり、室内にいたるまで執拗にくり返し用いられる。
ウィーン郵便貯金局/1910

ドローイング
|
|