|
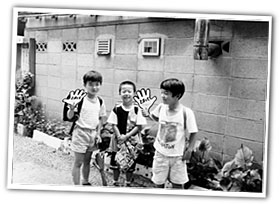 わたしたちはある「空間」を目で見たり、手で触れたり、中を歩き廻ったり、中で音の響きに耳を澄ましたりすることができます。わたしたちの空間認識は目や手や足でその空間を体験することから始まるといっていいでしょう。
わたしたちはある「空間」を目で見たり、手で触れたり、中を歩き廻ったり、中で音の響きに耳を澄ましたりすることができます。わたしたちの空間認識は目や手や足でその空間を体験することから始まるといっていいでしょう。
しかしまた、わたしたちは体験でなく思考の中で空間を共有することもできます。例えばものの長さはものさしを用いることによって何ミリというように数量化され、普遍性を帯びた情報として共有、蓄積、交換することができるのでわたしたちは長さを考えることができます。
しかし新聞に折り込まれた不動産の広告のような情報では空間を共有することはできません。駅徒歩何分、何平方メートル、外壁タイル貼りといったものさしだけでは空間は把握できないのです。
空間における目や耳から得た知識や感覚といったものを共有、交換可能な情報にする『ものさし(共通の感受性)』[西、1996、170ページ]とは空間の見え方や大きさ、形、機能、そこでの時間や質感、自然との関係といったことの総体であり、これが各々に内在するから空間を共有することができるのです。
『ものさし』を手に空間を見る、空間を「はかる」ことから空間は開かれるのです。
京都市左京区浄土寺(写真:長谷川知美)
|