|
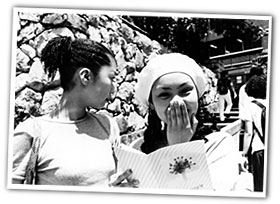 エジプトのピラミッドやギリシャのパルテノン神殿、日本の法隆寺を例に挙げるまでもなく、ひとは紀元前の昔から営々と建築し続けてきました。その数千年の歴史の中で「様式」あるいは形式というきまりごとが煮凝りのように、あるいは火山から流れ出た溶岩のように固まって今日に至っていて、それを時系列に沿って述べると建築史になり、面的な広がりにおいて述べると社会、文化論になります。そして様式というきまりごとは時間によって磨かれ、確固とした美を備えて、今なお建築を行うときの規範として生き長らえているのです。
エジプトのピラミッドやギリシャのパルテノン神殿、日本の法隆寺を例に挙げるまでもなく、ひとは紀元前の昔から営々と建築し続けてきました。その数千年の歴史の中で「様式」あるいは形式というきまりごとが煮凝りのように、あるいは火山から流れ出た溶岩のように固まって今日に至っていて、それを時系列に沿って述べると建築史になり、面的な広がりにおいて述べると社会、文化論になります。そして様式というきまりごとは時間によって磨かれ、確固とした美を備えて、今なお建築を行うときの規範として生き長らえているのです。
しかし様式は空間を直接規定するものではありません。時系列、地域を越えてわたしたちが空間を共有できるのは空間が様式の束縛から離れているからなのです。例えば茶を点てるとき、今では道具を置く位置も細かく決められていますが、茶のこころがそこにあるとは思えません。
逆にきまりごとはきまりごととして、そこに込められた意図をわたしたち自身の読み方で汲み取り、それをわたしたち自身の言葉で表現すればきまりごとの枠を越えた新鮮なものになるのではないでしょうか。そのときに問われるのはもはや様式ではなく、「作法」とも言うべき、作り手としての身だしなみだと思います。
読み手としては、そんな作り手の身振りの根にある倫理や価値感を掘り起こして、底に隠された『本質』を探ってみるのもひとつの手といえるでしょう。
京都市左京区北白川(写真:大島千秋) |