|
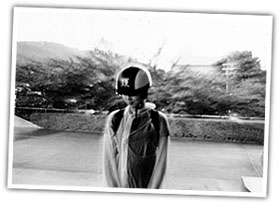 わたしのページでは『わたしたちは経験を生きている』[西、1996、57ページ]という認識を出発点にして、個々が持っている「空間」を『普遍性の方へ開いていく』[小林他1994、4ページ]思考の道筋を例示しようとしています。
わたしのページでは『わたしたちは経験を生きている』[西、1996、57ページ]という認識を出発点にして、個々が持っている「空間」を『普遍性の方へ開いていく』[小林他1994、4ページ]思考の道筋を例示しようとしています。
まず空間について、何からどのように考えて行けばいいのか、その手掛かりをわたしたち自身の経験に求め(さがす、よむ)、その中で直接経験する空間の『事実』[竹田 1989、58ページ](はかる~おどす)、間接的に判断する空間の『本質』(ためす~あらがう)をそれぞれいくつか具体的に紹介して空間の認識をゆるぎない『直観』[竹田、1989、50ページ]の方へ掘り下げていくという自らへの問いかけの参考として示し、最後にわたしたちがいま他者とともにここに在ることについて言及しています(あたためる~とる)。
空間という日本語は「建築」という言葉とともに実は明治になってから使われるようになった、比較的歴史の浅い言葉です。
では空間という言葉がなかった時代に空間はなかったのかというと、例えば「つかの間」という言葉が空間と時間の両方にまたがってあることで分かるように空間はあったと考えられます。
ここで空間を読むことがそのまま空間を創ることにつながる訳ではありませんが空間について考えるとき、近代の主観を客観に一致させようとする図式から脱却した、『自らに向かって問いかける』[西、1996、48ページ]という姿勢は行き詰まってしまった近代を越えて、他者とともに生きていける可能性を秘めているのではないでしょうか。
写真:京都市左京区岡崎(長谷川知美)
|